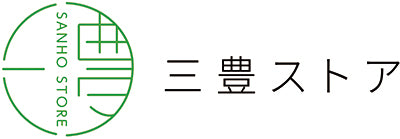「夜中に突然泣き出して、なかなか泣き止まない」「何をしてもダメで、親のほうが寝不足で限界」
このように、赤ちゃんの夜泣きに悩むママ・パパは少なくありません。原因がわからず不安になったり、自分の育児が間違っているのではと落ち込んだりすることもあるでしょう。
この記事では、赤ちゃんの夜泣きの原因や、月齢別に見られる傾向と対策、すぐに実践できる環境の整え方までをわかりやすくまとめました。さらに、実際に育児中のスタッフが活用している赤ちゃんの快眠グッズもご紹介します。
赤ちゃんも親もぐっすり眠れる夜を目指して、今日からできる対策を一緒に考えてみませんか。
- 1.そもそも夜泣きとは?知っておきたい基礎知識
- 夜泣きの特徴とは?寝ぐずりとの違い
- 夜泣きは深刻なことではない
- 2.夜泣きの原因と“快適な眠り”の環境づくり
- ①発達の変化による一時的な夜泣き
- ②生活リズムの乱れと日中の過ごし方
- ③感情や不安による目覚め
- ④寝室の温度・湿度・音・光といった環境要因
- ⑤ちょっとした不快感、体調不良
- 3.月齢別!夜泣き“あるある”と対策のポイント
- 0〜3ヶ月:昼夜の区別がつかず、夜も不規則に起きる
- 4〜6ヶ月:睡眠リズムの変化と“睡眠退行”の時期
- 7〜12ヶ月:分離不安と活動量の変化が影響
- 1歳〜1歳半:言葉が出る前の“伝えられないストレス”が影響
- 4.夜泣き対策におすすめの快眠グッズ
- 5. まとめ
1.そもそも夜泣きとは?知っておきたい基礎知識
「夜中に突然泣き出す」「昼間は機嫌がいいのに、なぜか夜になると泣き続ける」
子育て経験のある方なら誰でも抱える悩みですが、実はこの「夜泣き」、医学的にははっきりと定義されたものではなく、赤ちゃんの発達過程で起こりうる自然な現象とされています。
夜泣きの特徴とは?寝ぐずりとの違い
夜泣きとは、赤ちゃんが睡眠中に突然泣き出し、原因がはっきりしないまま泣き続ける状態を指します。
一方で「寝ぐずり」は、眠る前に泣いたりぐずったりして、入眠までに時間がかかる状態のことです。寝ぐずりは眠る前、夜泣きは眠った後に起きる、という違いがあります。
また、夜泣きの際には、授乳が済んでおり、おむつもきれいなのに泣いてしまうことも多く、親にとっては原因がつかみにくいことも特徴です。
夜泣きは深刻なことではない
夜泣きは、生後6か月〜1歳半ごろにかけて成長とともに増えるといわれています。成長の一過程と考えられており、赤ちゃんの脳や神経が発達している証拠でもあります。
「自分の育て方が悪いのでは」と責める必要はありません。まずは、赤ちゃんの夜泣きは自然なことであると理解し、深刻に受け止めすぎず、できることから対策していくことが大切です。
2.夜泣きの原因と“快適な眠り”の環境づくり

夜泣きが続くと、「どうしてこんなに泣くの?」「何がいけないの?」と不安になったり、イライラしてしまう方も多いはずです。子育てする側も睡眠不足になり、そんな中で泣き止まない赤ちゃんに向き合うのは心身ともに大きな負担になります。
夜泣きを改善するには、まず原因を知ることが大切です。そのうえで、赤ちゃんが安心して眠れる環境を整えることが、親子の睡眠改善につながります。
赤ちゃんの夜泣きには明確な“これ”という原因がないことも多く、いくつかの要因が複雑に絡んでいる場合がほとんどです。
①発達の変化による一時的な夜泣き
赤ちゃんの脳や神経は、生後数ヶ月で急速に発達します。
この発達にともない、睡眠の構造も大きく変化していきます。特に生後3ヶ月以降は、睡眠リズムが乱れる「睡眠退行(スリープリグレッション)」と呼ばれる時期があり、これまで比較的まとまって眠れていた赤ちゃんが、突然夜中に何度も起きて泣くようになることがあります。
これは赤ちゃんが浅い睡眠の回数が増え、ちょっとした刺激で目が覚めやすくなるためです。発達の一過程であり、特別な病気や異常ではありません。
②生活リズムの乱れと日中の過ごし方
赤ちゃんの体内時計は生後3〜4ヶ月頃から少しずつ整い始めますが、昼寝の時間や日中の活動量、朝起きる時間が不規則だと、夜に寝つきにくくなったり、夜中に何度も目覚めたりしやすくなります。
また、夕方以降に長い昼寝をしてしまうと、夜の眠りが浅くなり、結果として夜泣きが増えることもあります。起床・就寝の時間をなるべく一定にし、朝はしっかり自然光を浴びるようにすると、体内リズムが安定しやすくなります。
③感情や不安による目覚め
赤ちゃんはまだ言葉で不安を表現できませんが、日中に感じた緊張、不快な経験などが、夜になって泣くという形で表れることがあります。特に生後6ヶ月以降は「分離不安」が始まり、ママ・パパと離れることに強い不安を感じるようになります。
このような感情の揺れが夜間に影響し、「何をしても泣き止まない」といった状態につながることがあります。日中のスキンシップや、絵本や音楽などを使って入眠前の穏やかな時間を持つことで、不安を和らげることができます。
④寝室の温度・湿度・音・光といった環境要因
赤ちゃんの睡眠は環境の影響を大きく受けます。暑すぎる・寒すぎる・乾燥している・眩しい・騒がしいなどの状態は、大人以上に敏感に感じ取られてしまいます。
特に夏の夜は暑さや寝汗で目覚めることが多くなります。冷房を使う場合は、エアコンの設定温度を26〜28℃に設定し、適温になるように調整しましょう。
湿度は50〜60%が理想的ですが、乾燥すると鼻づまりの原因に、湿度が高すぎると寝苦しさやダニ・カビの原因になるため、加湿器や除湿機を使って調整しましょう。
また赤ちゃんの服装は、室温やエアコンの使用状況によって調節が必要ですが、薄手の肌着にスリーパーを重ねるなど、汗を吸って冷えない素材を選ぶと安心です。また、通気性のよい寝具を選ぶ工夫もしてみましょう。
音や光も睡眠を妨げる要因になるため、カーテンを遮光タイプにしたり、音の出る家電を寝室から遠ざけたりすると効果的です。
⑤ちょっとした不快感、体調不良
赤ちゃんは体調がすぐれないときや、身体のどこかに不快感があるときも夜泣きをしやすくなります。たとえば鼻が詰まって息苦しい、お腹にガスがたまっている、便秘気味でおなかが張っている、などの軽微な不快感が、睡眠中に目が覚める原因になることがあります。
泣き止まない状態が続き、発熱や咳、下痢、呼吸の異常などがある場合は、単純な夜泣きではなく体調不良が原因の可能性もあります。すぐにかかりつけの小児科へ相談しましょう。
3.月齢別!夜泣き“あるある”と対策のポイント

夜泣きは、赤ちゃんの発達段階によって、状態や対処のコツが変わってきます。
この章では、月齢別によくある夜泣きの傾向と、それぞれに合った対応方法を整理してご紹介します。
0〜3ヶ月:昼夜の区別がつかず、夜も不規則に起きる
この時期の赤ちゃんは体内時計がまだ未成熟で、昼夜の区別がついていません。夜泣きというよりも「数時間おきに目を覚ます」のが自然な状態です。
眠りが浅く、少しの刺激でもすぐに泣くことがありますが、これは赤ちゃんの生理的な特性です。
対策のポイント:
・朝はカーテンを開けて日光を浴びさせる・夜は照明を落とし、静かな雰囲気にする
・眠りにつく前はなるべく音や光などの刺激を減らす
昼夜の環境のメリハリをつけて、「夜は眠る時間」という感覚を少しずつ育てていきましょう。
4〜6ヶ月:睡眠リズムの変化と“睡眠退行”の時期
この時期になると、赤ちゃんの睡眠が深い眠りと浅い眠りに分かれてきます。特に4ヶ月ごろは「睡眠退行」が始まり、突然夜中に何度も起きるようになることがあります。 これまで比較的まとまって寝ていたのに、急に夜泣きが始まったというケースも珍しくありません。対策のポイント:
・寝かしつけの前に入浴・授乳・絵本など“入眠の流れ”を固定する
・昼寝は夕方遅くならないように調整する(15〜16時まで)
・「抱っこから布団へ」の流れをスムーズにする寝具を活用する
「毎晩同じ流れで寝る」ことが、夜中の目覚めにも安心感を与えるポイントになります。
7〜12ヶ月:分離不安と活動量の変化が影響
この時期の赤ちゃんは人見知りや分離不安が強くなり、「親と離れることへの不安」が夜泣きにつながることがあります。また、ハイハイやつかまり立ちなど身体活動が活発になり、日中の刺激が夜泣きとして現れることもあります。対策のポイント:
・日中はしっかり体を動かす遊びを取り入れる・寝る前の1〜2時間は静かに過ごし、興奮状態を避ける
・「親の気配」を感じられるアイテムを使う
赤ちゃんとたっぷり遊んで、穏やかな気持ちで眠れるよう“活動と休息のバランス”を意識しましょう。
「親の気配」を感じられるアイテムとしては、胎内音やおやすみ前の読み聞かせを録音した音声を流すおもちゃや、一定のリズムや音を繰り返すぬいぐるみ型の安眠グッズなどが効果的です。赤ちゃんが慣れ親しんだ音を聴くことで、夜中に目を覚ましたときも安心しやすくなります。
1歳〜1歳半:言葉が出る前の“伝えられないストレス”が影響
1歳を過ぎると自我が芽生え始め、「こうしたい」「イヤだ」という気持ちが強くなってきます。しかし、まだ言葉では十分に伝えられないため、そのフラストレーションが夜泣きに表れることがあります。この時期は卒乳や断乳の時期とも重なり、生活リズムが変化することも影響します。
対策のポイント:
・日中は子どもの気持ちを受け止める“共感的な関わり”を心がける
・夜間断乳や卒乳を進める場合は段階的に行い、昼間のスキンシップを増やす
・夜中の目覚めには焦って対応せず、まず様子を見てみる
赤ちゃんが夜に不安を感じにくくなるように、日中のうちにたくさんスキンシップや声かけをして、気持ちを安心させてあげることが大切です。
月齢・年齢によって見える世界や感じる不安は異なります。
何をしても泣き止まないという日が続いても、赤ちゃんが今どんな時期にいて、何を求めているのかを想像してあげるだけで、対応の方向性が見えてくることもあるのです。
4.夜泣き対策におすすめの快眠グッズ
夜泣き対策の基本は、赤ちゃんの様子をよく観察し、環境や生活リズムを整えていくことです。 それでも「あともう一歩、楽になりたい」と思う夜もあります。そんなとき便利なのが、赤ちゃんの寝かしつけや快適な睡眠をサポートしてくれる育児グッズです。ここでは、夜泣きの軽減に役立つ商品を、使用感や購入者の口コミ、スタッフのコメントも交えてご紹介します。ご自身の状況に合うものがあれば、ぜひ参考にしてみてください。
「ジオピロー」:通気性と安定感で赤ちゃんの“ぐっすり”をサポート

「ジオピロー」は、赤ちゃんの頭をやさしく支え、通気性の高い構造で、寝汗によるムレも軽減できるベビー枕です。絶壁頭の防止など、頭の形を整えるのが特長ですが、その高い通気性からも支持を集めています。
主な特長
・メッシュ構造で熱がこもりにくい・赤ちゃんの自然な頭の丸みにフィット、絶壁頭や斜頭症を防止
・丸洗いできて衛生的、暑い季節も安心
購入者の口コミ
「メッシュ素材で夏場にぴったり!洗濯できるのはありがたい」「暑い季節でも通気性の良さで寝苦しくなく使えそう」
「今まで枕を使っていなかったので嫌がるかな?と思いましたが爆睡してます!!」
ジオピローの詳細はこちら

商品ページ
「ハグマット」:背中スイッチ対策に。抱っこのまま寝かせられる安心感

赤ちゃんが眠ったと思って布団に置いた瞬間に泣く、いわゆる“背中スイッチ”に悩まされている方も多いのではないでしょうか。そこで役立つのが 「ハグマット」です。
赤ちゃんをハグマットにのせて抱っこし、寝かしつけたあと、マットごと布団にそっと移動させます。赤ちゃんを置いたときの刺激が少ないため、起こさずにそっと寝かせることができ、寝かしつけにかかる時間やストレスを軽減できます。
また素材の通気性が高く、そのまま寝かせても快適な睡眠を維持しやすくなります。
主な特長
・抱っこしやすい形状、軽量で抱っこしたときの腕や腰への負担も軽減・通気性がよく、オールシーズン使える
・洗濯機で丸洗いOK、いつでも清潔
子育て中のストアスタッフのコメント
「毎晩のように夜泣きで寝かしつけがやり直しになっていましたが、ハグマットを使ってからは一発で寝かしつけられる日も増えて、本当に助かっています。」(ストアスタッフ a.m)ハグマットの詳細はこちら

商品ページ
このように、ちょっとしたサポートアイテムを取り入れることで、赤ちゃんがぐっすり眠れる環境づくりがさらにスムーズになります。
5. まとめ
赤ちゃんの夜泣きにはさまざまな原因があり、すぐに改善するとは限りません。
しかし、月齢や発達に合わせて環境や関わり方を少しずつ見直していくことで、赤ちゃんも育児する側もラクになっていくはずです。
寝不足でつらい毎日が続くときは、赤ちゃんの快眠に役立つグッズを使ってみたり、ときには周囲にサポートを求めることも必要です。無理をしすぎず、今日できることから一つずつ実践してみることで、赤ちゃんがぐっすり眠れる夜が少しずつ増えていくでしょう。