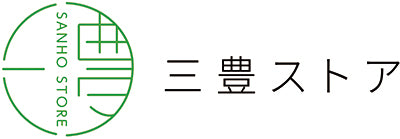赤ちゃんが動き始めると、成長に喜びを感じる一方で、「思わぬ事故が起こるかもしれない」と心配になることもあります。「ヒヤリハット」とは、幸い事故には至らなかったものの、ヒヤリとする事象のことです。
家庭内は安心できる場所と思いがちですが、実はさまざまな危険が潜んでいます。
この記事では、赤ちゃんとの生活の中で起きやすいヒヤリハットの事例と、具体的な対策や役立つアイテムを紹介します。事故を未然に防ぎ、安全で快適な子育て環境を整えましょう。
- 1. 家庭内で起こりやすい赤ちゃんの事故とは?
- 2. 家庭内の危険を場所別に徹底チェック
- リビング:赤ちゃんが長く過ごす場所
- 台所:最も事故リスクが高い危険地帯
- 階段・段差:一瞬の転落が大事故に
- 寝室・寝具まわり:静かな環境でも油断禁物
- 3. 事故の種類別 安全対策まとめ
- 転倒・転落を防ぐためにできること
- 誤飲・誤食を防ぐための習慣づくり
- やけどを防ぐためにできること
- 4. 赤ちゃんの安全を守る小さな意識と習慣
- 家具の配置を見直す
- 危険なものに物理的に近づけない
- 日常の物の置き場所を“見える化”する
- 成長に合わせて見直す
- 5. 赤ちゃんを守る!おすすめ育児グッズ活用法
- 転落を防止する「ベッドガード」
- 転倒や頭のケガを防ぐ「プレイマット」
- 安全な行動範囲をつくる「ベビーサークル」
- 吐き戻しによる誤嚥・窒息を防ぐ「傾斜クッション」
- 窒息事故を防ぐ通気性に優れたベビー枕
- その他、育児を安全・快適にするサポートアイテム
- 6. まとめ
1. 家庭内で起こりやすい赤ちゃんの事故とは?
赤ちゃんとの暮らしでは、家庭内に潜む危険に目を向ける必要があります。成長とともに活動範囲が広がり、思わぬ事故につながるリスクも高まるため、早めの対策が重要です。消費者庁の令和2年のアンケート調査によると、「家の中で14歳以下の子どもの事故やヒヤリハットを経験した」と回答した人は24%にも上りました。
事故の種類としては「落ちる」が最も多く、特に階段で多く発生しています。事故の場所としては台所、リビング、階段の順で多くなっています。年齢別で事故が最も多かったのは1歳児でした。
また、事故に至らなかったものの「ヒヤリとした」「危なかった」と感じた出来事も多数報告されており、家庭内には大きな事故につながるリスクがあることが分かります。
これらの事故は特別な環境で起きたわけではなく、「ちょっと目を離したすきに」「まさかこんなことで」という日常のシーンで発生しているのです。
赤ちゃんの行動は予測が難しく、どれだけ注意していても100%防げるとは限りませんが、あらかじめ備えることで事故を大幅に減らすことができると言われています。
2. 家庭内の危険を場所別に徹底チェック

家の中は一見安全に見えても、赤ちゃんにとっては危険がたくさん潜んでいます。
特に、ずりばいやハイハイ、つかまり立ちが始まる頃は、赤ちゃんの視野や行動範囲が広がり、大人が気づかない場所や物に手を伸ばすようになります。
ここでは、赤ちゃんが暮らす空間を見直すために、場所別に注意すべきポイントを整理します。
リビング:赤ちゃんが長く過ごす場所
家族が集まり、赤ちゃんが自由に過ごす時間が多いリビングは、ヒヤリハットが起きやすい場所でもあります。特に注意すべきなのは、・テーブルやテレビ台の角:目線や頭の高さにぶつかり、額や顔にけがをしやすい
・コード類や電源タップ:ひっぱって倒したり、口に入れてしまうおそれ
・カーテンやブラインドのひも:首に巻きつく事故も報告されている
・リモコン・小物・文具:電池やボタンなど、小さな部品が取れて誤飲のリスクになる
▶︎対策の基本:
・家具の角にはソフトガードを取り付ける
・床にコードを這わせないように束ねて壁沿いに設置
・小物は手の届かない引き出しや棚へ移動
台所:最も事故リスクが高い危険地帯
調理中に大人が目を離しがちになるキッチン周辺も、事故が多い場所です。特に注意すべきポイントは以下のとおりです。
・床に落ちた小さな食材・包装:ハイハイ中に拾って口に入れる危険性
・鍋、ポット、炊飯器など:取っ手に触れたりコードを引っぱって熱湯をかぶる、蒸気でやけどする
・包丁・ハサミなどの刃物:シンク下や低い引き出しに入っている場合、開けて取り出してしまう
▶︎対策の基本:
・キッチンの出入口にはベビーゲートやサークルでバリアをつくる
・調理器具や調理家電を熱いまま放置せず、赤ちゃんの手の届かない場所で使う
・引き出しや扉にはチャイルドロックを設置
階段・段差:一瞬の転落が大事故に
ハイハイやつかまり立ちを始めた赤ちゃんにとって、階段は特に危険です。2〜3段のちょっとした段差でも、赤ちゃんにとっては大きな高低差。頭から落ちる可能性もあります。▶︎対策の基本:
・上下どちらにも開閉式のベビーゲートを設置
・滑りやすい素材の階段には滑り止めマットを敷く
・手すりの隙間にも体が挟まらないよう、専用のフェンスを使う
寝室・寝具まわり:静かな環境でも油断禁物
寝かしつけやおむつ替えで使用する寝室も、意外な危険が潜んでいます。次のようなポイントに注意が必要です。
・ベッドやおむつ台からの転落:数秒目を離しただけで起こる
・寝具・まくらによる窒息:顔が埋もれたり、毛布が顔にかかり呼吸を妨げる
・吐き戻しによる誤嚥:授乳直後に寝かせると、吐き戻したミルクが気道に詰まることも
▶︎対策の基本:
・寝具はできるだけシンプル・軽量・通気性のよいものに
・授乳後すぐは、少し傾斜をつけた姿勢で様子を見る
赤ちゃんの行動は日々変化していきます。昨日まで届かなかった場所に、今日は手が届くかもしれません。
「このくらいは平気だろう」と油断せず、“今の月齢で届く範囲・危険なもの”を定期的に見直すことが大切です。
3. 事故の種類別 安全対策まとめ

赤ちゃんが安心して過ごせる環境づくりには、特別な設備だけでなく、日常生活の中でできる小さな工夫の積み重ねが必要です。毎日の暮らしの中でできる具体策を、「事故の種類別」に整理してご紹介します。
転倒・転落を防ぐためにできること
転倒や転落は、赤ちゃんの事故の中でも特に多く報告されています。注意が必要なのは、以下のような場面です。
・ソファやベッドの上に寝かせて目を離したすきに転落
・おむつ替え台や抱っこからの落下
・フローリングで滑って頭を打つ
▶︎対策のポイント:
・赤ちゃんを高い場所に寝かせたまま離れない
・抱っこ紐やおんぶの際には、バックルの留め忘れがないか再確認
・フローリングには滑りにくい素材のマットを敷いて衝撃を緩和
誤飲・誤食を防ぐための習慣づくり
赤ちゃんは口を使って物を確かめる時期があり、何でも口に入れてしまいます。誤飲事故を防ぐためには、手に届く範囲を「安全ゾーン」に保つことが重要です。
▶︎対策ポイント:
・床に小物や包装紙などが落ちていないか、こまめにチェック
・電池、磁石、医薬品などは必ず高い場所へ保管
・テーブルの上にスマホやリモコンなど誤飲につながる物を放置しない
・赤ちゃんが遊ぶエリアの収納にはチャイルドロックを設置
やけどを防ぐためにできること
赤ちゃんの皮膚はとても薄く、わずかな温度でもやけどにつながります。家電や調理器具だけでなく、熱い飲み物にも注意が必要です。
▶︎対策ポイント:
・加湿器や電気ポットはコードごと届かない場所に設置
・テーブルクロスを引っ張って熱い飲み物がこぼれないようにする
4. 赤ちゃんの安全を守る小さな意識と習慣
ここまで、赤ちゃんが安全に過ごすための対策をご紹介しましたが、実はちょっとした意識や習慣が、事故を未然に防ぐ大きな力になります。いつもの「目線」を変えるだけで危険が見える
赤ちゃんの世界は、常に床に近い高さで広がっています。そのため、大人が立ったままでは気づかない危険が、赤ちゃんには手の届く範囲に存在しているのです。
▶︎実践ポイント
・ハイハイの高さで部屋の中を移動してみる
・見下ろすのではなく、赤ちゃんの目線でコンセント、家具、落下物などを確認
・おもちゃやお菓子の包装、紙くずなどが床に落ちていないかチェック
この“目線を合わせる”だけの習慣が、リスク軽減につながります。
家具の配置を見直す
赤ちゃんの動線上にある家具の位置や形状も、事故の原因になり得ます。転倒時に頭を打ちやすい角のあるローテーブルや、引き出しが手前に開く棚などは、配置や向きを見直すことでリスクを大きく下げることができます。
▶︎実践ポイント
・頭の高さに角がくる家具を移動する、またはコーナーガードを取り付ける
・家具と壁の隙間に赤ちゃんが入り込まないようにスペースを埋める
家具の「設置場所」だけでなく、「どう倒れるか」「どこに落ちるか」という視点でも見直しておくと安心です。
危険なものに物理的に近づけない
動き回るようになると、危ないものから赤ちゃんを離す必要が出てきます。「見守る」「注意する」だけではカバーしきれない状況を減らすには、物理的なバリアを設けることも重要です。
▶︎実践ポイント
・キッチンや浴室など立ち入り禁止エリアにはベビーゲートを設置
・ベビーサークルを活用して、安全な遊び場を確保
日常の物の置き場所を“見える化”する
誤飲やケガを防ぐためには、「これは大人のもの」「これは赤ちゃんのもの」という置き場所のルールを明確にすることが効果的です。▶︎実践ポイント
・引き出しや収納には、赤ちゃんOK・NGを分類する
・家族内でルールを共有し、うっかり放置を防ぐ
・危険なアイテムは“そもそも出さない”ことを習慣化する
使い終わったものをすぐ戻す、テーブルの上を常に片づけておくなど、基本的な習慣が安全性を左右します。
成長に合わせて見直す
赤ちゃんの成長はとても早く、昨日まで届かなかった棚に手が届くようになっていることもあります。一度対策をしたからといって安心せず、月齢や行動の変化に応じて定期的にチェックすることが大切です。
ハイハイ・つかまり立ち・歩き始めなど成長の節目ごとに、習慣を見直しましょう。
このような日々の習慣化、意識づけだけでも、事故を未然に防ぐことができます。
5. 赤ちゃんを守る!おすすめ育児グッズ活用法
赤ちゃんを家庭内の事故から守るためには、日々の気配りや工夫に加え、専用の育児グッズを上手に取り入れることが効果的です。一瞬の油断や、赤ちゃんの予測できない行動も、アイテムを活用することでリスクを大きく減らすことができます。
家庭内の安全対策に役立つアイテムを目的別に紹介します。
転落を防止する「ベッドガード」

赤ちゃんが歩けるようになると、ベッドの上でも動き回るようになります。動きが活発になる1歳半ごろからは、就寝中や目を離したすきにベッドから落ちてしまう危険性が高まります。
そんなとき便利なのが、転落防止のためのベッドガードです
【おすすめアイテム:ベビーガードメッシュ】
・対象年齢:1歳半から使用可能
・通気性の良いメッシュ素材とやわらかなクッション構造
・高さ調整ができ、さまざまなベッドタイプに対応
ワンオペ育児中など、どうしても赤ちゃんから目を離してしまう場合にはベッドガードがあると安心です。取り返しがつかなくなる前に、事故対策をしましょう。
転倒や頭のケガを防ぐ「プレイマット」

フローリングなどで赤ちゃんがハイハイやつかまり立ちをする際、心配なのが転倒時の頭部への衝撃です。
床の硬さを和らげるプレイマットは、非常に効果的な安全対策アイテムといえます。
【おすすめアイテム:もちもちプレイマット】
・優れたクッション性で転倒時の衝撃を緩和
・走っても滑りにくいエンボス加工
・適度な厚みで騒音も緩和
プレイマットは他にもさまざまな選択肢がありますので、チェックしてみてください。
赤ちゃんが毎日遊ぶスペースに敷いておけば、万が一の転倒でも安心。マット自体が赤ちゃんにとっての「安心できるエリア」となり、自分からその上で遊ぶ習慣も身につきます。
安全な行動範囲をつくる「ベビーサークル」

ハイハイや伝い歩きが活発になると、赤ちゃんは思わぬ場所にまで移動してしまいます。
刃物や熱源のあるキッチン、段差のある玄関や階段など、危険な場所に近づかせないためには、行動範囲そのものを制限する方法が最も確実です。
【おすすめアイテム:ベビーサークル プレイマット】
・ベビーサークルとしても、プレイマットとしても使える
・コンパクトに折りたためて持ち運びにも便利
・家具や床を傷つけにくい滑り止め付き
他にも、機能に応じてさまざまなベビーサークルがあります。
ベビーサークルは、赤ちゃんの遊び場を「安全なエリア」として確保できるだけでなく、親が家事などで手が離せないときにも安心して見守ることができます。
吐き戻しによる誤嚥・窒息を防ぐ「傾斜クッション」

授乳後に赤ちゃんが吐き戻してしまい、それが気道に入ってしまう誤嚥・窒息事故は、静かに起こるためとても危険です。
予防のためには、授乳後すぐに寝かせるのではなく、上半身を軽く起こした姿勢を保つことが重要です。
【ロトトクッション】
・クッションごと移動できるため、抱っこからおろした瞬間に起きてしまう「背中スイッチ」にも対応
・洗い替え用カバー付きで衛生面も安心
窒息事故を防ぐ通気性に優れたベビー枕

就寝時の窒息事故を防ぐためには、寝具の通気性や、赤ちゃんが楽な姿勢でぐっすり眠れる快適性が重要です。
【おすすめアイテム:ジオピロー】
・「呼吸する枕」と呼ばれるほどの高い通気性
・蒸れにくいため寝汗・あせも対策にもなる
・立体構造で赤ちゃんの頭を優しく支え、仰向けで寝かせても絶壁頭になりにくい
その他、育児を安全・快適にするサポートアイテム
上記以外にも、安全性を追求したさまざまな育児グッズがあります。
・コンセントカバー・チャイルドロック:指突っ込みや開閉による事故を防止
・滑り止め付きスリッパ・マット:赤ちゃんを抱っこした状態での転倒防止
・通気性の高いブランケット:顔を覆うことでの窒息防止
これらを必要に応じて組み合わせながら、無理なく続けられる対策を選ぶのがポイントです。
育児アイテムは、単に「便利にする」ためのものではありません。
赤ちゃんの安全と、育児を担う方の安心感や余裕を生み出すための存在でもあるのです。
6. まとめ
赤ちゃんとの暮らしでは、家庭の中に思わぬ危険が潜んでいます。大がかりな準備をしなくても、家具の配置を見直す、段差を確認する、安全な遊び場を確保するなど、日々のちょっとした工夫でリスクを減らすことができます。
また、プレイマットやベビーサークルなどの育児グッズをうまく活用すれば、赤ちゃんの安全はもちろん、育児中の方の安心やゆとりにもつながります。
備えることで防げる事故はたくさんあります。赤ちゃんの成長に合わせて、今できる安全対策からはじめてみましょう。